データ・プログラムの一時保存を行うメモリー
メモリーとは、データを記憶する部品のことです。英語でmemoryとは記憶を意味します。
メモリーは、大きく分けてと読み書き両方できるRAM(ラム)と読み出し専用のROM(ロム)がありますが、一般的にメモリーという時は、RAMであるメインメモリーのことを指します。スマートフォンやタブレットでは、単にRAMといいます。
データやプログラムを 一時的に記憶する部品で、コンピューターでは 主記憶を担当します。
分かりやすく例えると机や作業台です。何かの課題に取り組んでいるとします。書類や辞書を並べたり、筆記用具をおいたり、参考書を開いたりします。
机の上が広ければ広いほど作業はしやすくはかどります。それと大変似ています。
メインメモリーもパソコンを使っているときや何かのプログラムを開くときに、作業台のように利用されます。そのためメモリーの容量は、パソコンの動作速度に影響を及ぼします。
メモリーの確認
デスクトップ上 右クリック→ディスプレイ設定→詳細情報。またはコントロールパネルからシステム。
実装メモリ(RAM)の項目です。
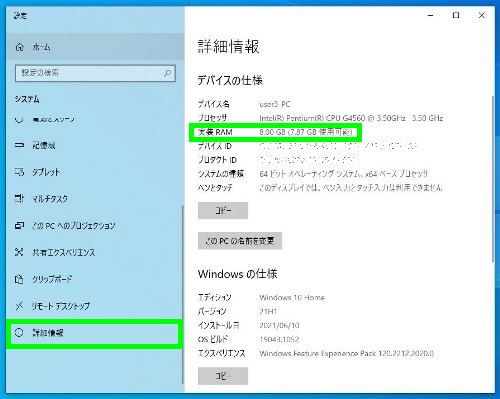
デスクトップパソコン用メモリー。DIMMともいいます。
基盤(緑)や端子部分(赤)からなる モジュールと、基板上の DRAMチップ (水色)などで構成されています。端子部分の切り欠きの場所がメモリーの種類・規格によって違ってきます。
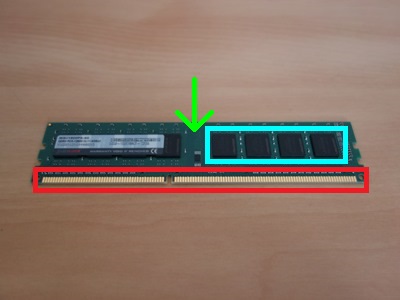
ノートパソコン用メモリー。デスクトップ用のメモリーより一回り小さくなります。SO-DIMMともいいます。

メモリーはマザーボードのメモリースロットに取り付けられています。

ノートパソコンのメモリースロット。

一体型パソコンは、内部構造がノートパソコンと似ているため、メモリーもノートパソコンと同じものが使われることがほとんどです。
主記憶
パソコンの電源を入れてOSを起動しているとき、プログラムを起動させているとき、ファイルやフォルダを開いたときなど、すべてのデータはハードディスクから読み込まれ、一旦 メモリー上におかれます。
メモリーは アドレス(番地)で区分けされていて、ここにデータが入っていきます。
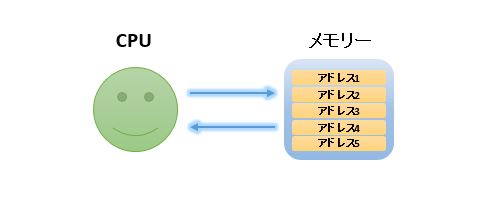
このメモリーにあるデータをCPUが読み書きして、処理したものを再度メモリーへ渡します。
例えば Excelなどで「名前を付けて保存」としたときに、メモリーからハードディスクやSSDに書き込みが行われます。
このようにメモリーは、作業机のような役割があり、CPUとは非常に密接な関係にあります。マザーボード上でハードディスクよりメモリーの方がCPUに近い場所にあるのもこうした理由です。
また 揮発性メモリーであり、パソコンの電源を切るとメモリー上からデータはなくなります。
容量
メモリーの容量とは、2進数の8ビット、1バイトを基準としてどれだけのデータを一時的に保存できるかということを表しています。
昔のWindows 98などのパソコンでは、メモリー1枚の容量は32MBや64MBなどでしたが、現在のメモリーも32MBや64MBの延長で、倍数になっていることが分かります。32MBの8倍が256MBなど。
256MBの倍数と覚えるとわかりやすくなっています。1024MBで1GBです。
市販されているメモリーは512MB、1GB、2GBなどがあり、最近では4GBや8GBのメモリーが使われるようになってきています。
メモリーの容量が少ないと、データのおき場所が足りない、確保できないということになり、パソコンの動作は遅くなる傾向があります。
種類・規格
メモリーには種類・規格があります。メモリーの出された時期によってメモリーの性能や切り欠き部分が異なります。新しいメモリーであるほど、転送速度が速く 容量の大きいものが増えています。
大きく分ける
メモリーには、主に以下のような規格があります。(上が新・下が旧)
- DDR5
- DDR4
- DDR3
- DDR2
- DDR
- SDRAM
DDR2やDDR4の正式な名称は、DDR2 SDRAM、DDR4 SDRAMです。単にSDRAMというときは旧規格のメモリーかメモリーそのものを指します。DDRは、ダブルデータレートの略で旧規格のSDRAMとは動作原理が異なり、現在でも高速化が進んでいます。
細かく分ける
またメモリーの規格はもう少し細分化して以下のように分けることもできます。(上が新・下が旧)
- DDR5-4800・・・PC5-38400
- DDR4-3200・・・PC4-25600
- DDR4-2666・・・PC4-21300
- DDR4-2400・・・PC4-19200
- DDR4-2133・・・PC4-17000
- DDR3-1600・・・PC3-12800
- DDR3-1333・・・PC3-10600
- DDR3-1066・・・PC3-8500
- DDR2-800・・・PC2-6400
- DDR2-667・・・PC2-5300
- DDR2-533・・・PC2-4200
- DDR-400・・・PC3200
- DDR-333・・・PC2700
- DDR-266・・・PC2100
DDRからDDR4は、さらに3~4つに分かれています。他に実際にはパソコンであまり採用されなかった規格として DDR3-800/PC3-6400やDDR2-400/PC2-3200というのもあります。
これらのメモリーの規格は、半導体標準化団体 JEDECにより規格化されています。
数字は単純に転送速度を示しています。同じDDR3やDDR4のメモリーでも、数字の大きいメモリーほど転送速度は速くなります。DDR4-2666などを チップ規格、PC4-21300を モジュール規格といいます。チップ規格を8倍するとモジュール規格になります。
Windowsのシリーズ
DDRのメモリーとWindowsは、ある程度関係しているところがあります。必ずしもこのような決まりがあるわけではないのですが、概ね以下のようになります。
- DDR4・DDR5・・・Windows 11
- DDR4・・・Windows 10
- DDR3・・・Windows 7、8
- DDR2・・・Widnows XP、Vista
- DDR・・・XP
パソコンに増設できるメモリーは、CPUやマザーボードに左右されます。
それぞれのパソコンには対応したメモリーというのがあり、チップ規格・モジュール規格が決まっています。
互換性
パソコンによっては、DDR2のすべてのメモリーが対応しているということもあります。この場合は、DDR2-800とDDR2-667をパソコンに付けても正常に動作します。
またDDR3-1600とDDR3-1333に対応していることもあります。この場合も、両方のメモリーをそれぞれ使うことができます。
メモリーには 下位互換性があるため、DDR2-800とDDR2-667のメモリーが付いていた場合、DDR2-667の速度で動作するようになっています。DDR2-800がDDR2-667の速度に合わせて動作します。
デュアルチャネル
デュアルチャネルとは、パソコンに同じ規格、同じ容量のメモリを2枚取り付けることにより、転送速度を向上させる技術のことです。
近年のパソコンは、ほとんどデュアルチャネル対応になっています。
パソコンに内蔵されているメモリーや販売されているメモリーが、x2や2本1組になっていることが多いのは、デュアルチャネルを考慮しているためです。
デュアルチャネル対応のパソコンでは、例えば4GB×1枚のメモリーより 2GB×2枚、8GB×1枚のメモリーより 4GB×2枚のメモリーのほうが、理論上 転送速度が速くなります。体感できるかどうかは、利用形態などにもよります。
3本1組で使うものを トリプルチャネルといいます。トリプルチャネルは一部のパソコンで使用されています。
VRAM
Video RAMの略。ビデオメモリー。ディスプレイに描画するためのグラフィック用メモリーです。
メモリーは通常のデータのおき場所以外にも、グラフィック用の領域も確保しています。
実際に搭載されている物理的なメモリー容量と、表示されているメモリー容量や使用可能メモリーと誤差があるのは、大抵 このVRAMで領域が予約されているためです。
画面描画ができないとパソコンは使えないため、VRAMは優先的にメモリーから領域を確保しています。
メインメモリーと共有しますが、グラフィックボードなどが付いていると、VRAMは メインメモリーとの共有ではなくグラフィックボードのものが使われます。
仮想メモリ
ハードディスクやSSD上に仮想的に確保されたメモリー領域。
メモリーが不足しているときに、仮想メモリにデータを退避させたり、メモリーに戻したりします。
仮想メモリは Windowsが管理していて、適切な設定になっているため通常扱うことはほとんどありません。